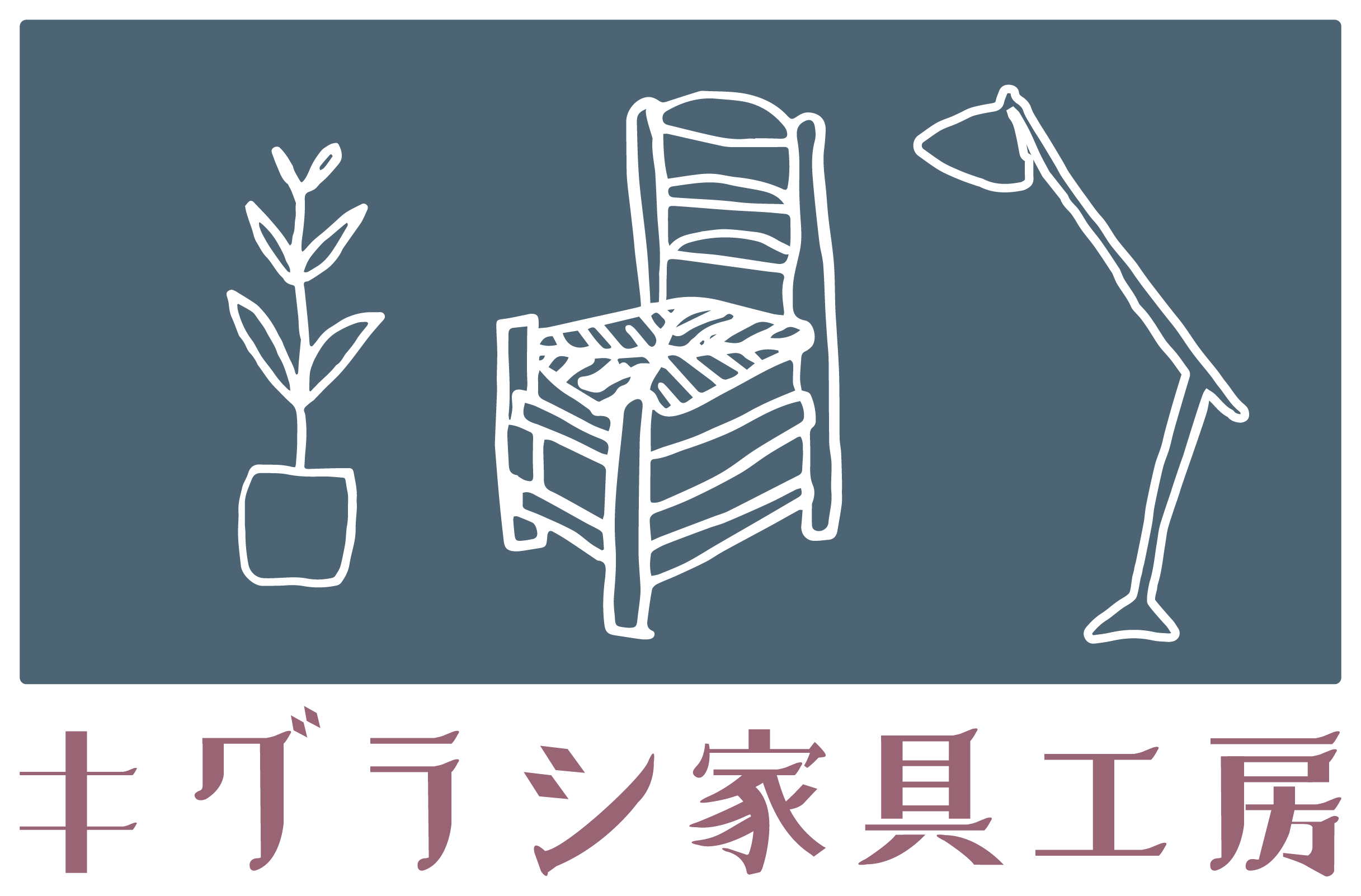このページではキグラシ家具工房のオリジナルちゃぶ台をご紹介します。
キグラシ家具工房のちゃぶ台は3種類!!
1.突っ張り板仕様の折れ脚
こちらはとてもレトロで懐かしいデザインですが、骨董など、昔ながらのちゃぶ台で最も多いのがこのタイプの畳み方かと思います。







サイズはやや小ぶりでチョットした時に持ち出しやすいサイズ感。
直径70cmと80cmを基本サイズとして販売しております。
基本サイズ:70サイズ/直径約70cm×高さ約28cm(折り畳み時約8cm)
80サイズ/直径約80cm×高さ約30cm( 折り畳み時約8cm)
※こちらの仕様の場合、構造上、高さを高く変更することはできません。
※高さをもう少し高く変更したい方は次にご紹介する「ボタン式」か「折れ脚金具式」タイプをおススメします。
古い天板を再利用
古家具、骨董として流通する古いちゃぶ台には、今ではなかなか手に入りにくいような良い材料が多く使われています。
特に天板は昨今では貴重な幅広の広葉樹が使われていることが主なので、これは十分、再利用の価値があると思っています。
そこで、当工房ではそんな古いちゃぶ台を入手した際、その天板だけを再利用して使うこともあります。
そうしてできたちゃぶ台は、古材の持つ独特な魅力と、新たにつくった脚との組み合わせにより、実用的かつ、個性豊かな表情のあるちゃぶ台としていっそうの存在感を放ちます。






2.ボタン式タイプの折れ脚

比較的折れ脚ちゃぶ台が普及してから時期を経た後期につくられるようになった構造だと思います。
単独、または二本の脚ごとにボタンを押した状態で畳む方式で、脚を開くと内部に仕込んだバネにより、ボタンが幕板の溝にハマることで固定されます。
こちらも古材天板を仕上げ直して組み合わせる場合があります。






基本サイズ:直径80cm×H30cm(折り畳み時約8cm)
※こちらの仕様は直径80cmと90cmを基本としていますが、わりと大きなサイズにも対応しやすく、高さ変更可能です。
3.折れ脚金具タイプ

どうしても昔ながらの工法で折れ脚をつくるのには、手間がかかります。
そこで裏側の趣は薄れますが、折れ脚金具を使用することで製作時の効率を上げ、天然木の折れ脚ちゃぶ台をリーズナブルな価格でご提供できる様、努めたタイプです。






基本サイズ:80サイズ/直径約80cm×高さ約30cm(折り畳み時約8cm)
90サイズ/直径約90cm×高さ約30cm( 折り畳み時約8cm)
※こちらの仕様でも80cm、90cmを基本としていますが最大Φ120cmまで対応でき、高さ変更も可能です。
受注生産の場合
オンラインショップ上でみつからなかったり「sold out」となっている場合、受注生産でお作りすることができます。(但し古材を使ったものは不可)
下記の料金表をご参考に、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 樹種 | Φ70cm | Φ80cm | Φ90cm | Φ100cm | |
| 突っ張り板式 | クリ | 62000円 | 70000円 | – | – |
| ボタン式 | クリ | – | 70000円 | 75000円 | 81000円 |
| 折れ脚金具 | クリ | 36000円 | 39000円 | 42000円 | 46000円 |
※価格は定期的に見直しているため、予告なく変動することがあります。
※樹種や形状、サイズの変更など、可能な範囲で対応させて頂きますので、まずはお問い合わせ頂けると幸いです。
どうぞお気軽に⇩⇩⇩